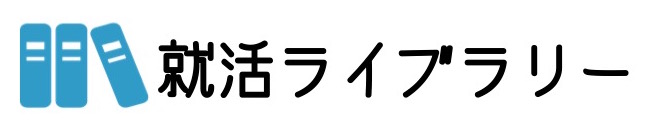こんにちは、就活ライブラリー編集長のそるてぃーです。選考が進むにつれて「グループディスカッションがうまくいかない」「グループディスカッションで落ちてしまう」「グループディスカッションの練習って、どうすれば効果的なの?」と悩んではいませんか?就職活動でグループディスカッションは避けて通れない選考の一つです。企業が求めるスキルをアピールするためには、事前の練習が成功の鍵となります。本記事では、初心者でも実践しやすいグループディスカッション練習方法を具体的に解説し、グループディスカッションの練習ができるイベント3選もご紹介します。短期間で自信をつけ、選考突破を目指したい方はぜひ参考にしてください!
【結論】GDは場数が最優先。一日で対策できるイベントに参加しよう
ジョブトラ

【就活生10万人以上が参加した早期内定の登竜門】と呼ばれるジョブトラは、自己分析や企業分析など、内定獲得までの就活ステップの基礎を学びながら本選考ワークを体験できる総合型の就活イベントです。大手企業のインターンや本選考で取り入れられている難解なビジネスゲームを実践できるのが他にはない特徴です。7社程度の参加企業から、学歴やガクチカ関係なく当日のワークの言動で評価された場合は、特別選考スカウトを受けることができます。
- 【就活生10万人以上が参加した早期内定の登竜門】
- ビジネスゲームでインターンシップのプチ体験が出来る
- 学歴やガクチカ関係なく、イベント当日の言動だけで特別スカウトがもらえる
- 少人数の座談会で企業の人事と会える
DyDo、世田谷自然食品、デジタルホールディングス(オプト)、TRYグループ、PERSOLなど
伊藤忠商事、三菱商事、味の素、サントリーホールディングス、トヨタ自動車、パナソニック、花王、損害保険ジャパン、ファーストリテイリング、日清食品、ブリヂストン、キリンビール、東京海上日動火災保険、電通、博報堂、グーグル、楽天グループ、アクセンチュア、KDDI、パソナ、ディー・エヌ・エー、NTTドコモ、三井住友銀行、住友生命保険、野村證券など
グループディスカッション(GD)とは?
GDとはグループディスカッションの略称で、採用企業が学生を選考するための方法の一つです。具体的には数人のグループに別れ、同じテーマについてそれぞれのグループで議論し結論を導き出す過程を採用担当が評価し合否をつけるというものです。一般的には自社とマッチしない学生をふるい落とす「足切り」として採用されることが多く、特に応募人数の多い大手企業がメインに採用しています。例外的に最終選考に組み込む企業もありますが、多くが選考の序盤に取り入れています。
企業がグループディスカッションを採用する理由

企業がグループディスカッションを選考方法として取り入れる理由は、大きく分けて2つあります。1つ目の理由は、「効率よく採用をするため」です。企業は一人でも多くの学生と出会い自社とマッチしている学生を見極めたいところではありますが、一人一人と面接している時間や人件費などのコストはありません。そのような背景から短時間で多くの学生と出会い、正確に評価できる選考方法としてグループディスカッションを採用しています。また、先述した通り「面接する人の人数を減らす」という観点で序盤にグループディスカッションを行うことが多くなっています。2つ目の理由は、「チームワーク力を見極めるため」です。面接は1対1の選考のため協調性を見極めるのが難しくなります。働く上で、チームワークは必要不可欠な要素のためチーム内でどのようにコミュニケーションを取れるかをグループディスカッションを通じて見極めているのです。
グループディスカッションの流れ

グループディスカッションは大きく分けて6つのフローが存在します。それぞれ具体的にはどのようなことをすべきなのか詳しく解説していきます。

グループ分けをされたら自己紹介から始めましょう!笑顔で元気よく「大学名+名前と一言短い挨拶」を伝えられればOKです!明るく話しやすい雰囲気を与えられるように心がけましょう!!
①役割・時間配分
まずは役割と時間配分を決めていきます。役割は、「司会・ファシリテーター」「書記」「タイムキーパー」「監視役」「アイデアマン」「発表者」に分かれます。時間配分は、議論時間やテーマによって臨機応変にその場で決めなければいけません。グループディスカッションの経験値が豊富だと、時間配分もうまくできるので練習の機会を増やすことをお勧めします。
②課題を定義
次に、テーマの前提を定義していきます。与えられたテーマや課題の趣旨を全員で正確に理解し、議論の方向性を明確にする段階です。このステップが不十分だと、議論が脱線したりグループ内の認識のずれが生じやすくなります。

「少子化対策を提案してください」というお題に対して前提条件を確認しなかった場合、
Aさん:全国の少子化対策を考える
Bさん:ある特定の地域の少子化対策を考える
のような認識のズレが生じる場合があります。ズレていることに気づかず話し合いが進んでしまった場合、お互いの意見が噛み合わず最初から議論をし直す必要があり時間ロスに繋がります。
5W(「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」)で整理すると漏れなく認識をすり合わせられます。
③現状分析・課題特定
現状を正確に把握し、課題の背景や問題点を具体化する段階です。これにより、アイデアの方向性が明確になり、解決策の実効性が高まります。主観に頼りすぎず、客観的な視点で現状を分析することが大切です。「なぜその問題が発生しているのか」「どんな影響があるのか」を具体的に掘り下げ、議論の土台を固めましょう。
④アイディアを出し合う
※画像を入れる※
現状と理想の乖離を埋めるためのアイディアを出せる限り出し尽くします。批判を避け、どんな意見も肯定的に受け入れる「ブレインストーミング」の姿勢が大切です。特定の人だけが発言せずに、全員が平等に意見を述べられる環境を作りましょう。
⑤アイディアを整理する
出されたアイデアを絞り込み、実現可能性や効果を基準に優先順位をつける段階です。議論の具体性が高まり、結論に向けた道筋が明確になります。ポイントとしては、評価軸を複数設定しどのアイディアが前提確認で設定したお題を解決できるか、定量的に検証します。
⑥結論出し・発表
結論が論理的であるか、説得力があるかを最終確認します。発表者だけでなく、チーム全員が議論内容を把握し、合意が取れているかということも重要です。発表に関しては、簡潔かつ明確な発表を心がけましょう。
グループディスカッションの役割

司会・ファシリテーター
グループディスカッションの進行を行い、メンバー間の意見交換を促進するリーダー的な存在です。グループディスカッションの中心人物になるため目立つことはできますが、全体を俯瞰する力や傾聴スキル・リーダーシップ力・論理的思考力など様々なスキルをバランスよく発揮する必要があるため、難易度が高いポジションです。
書記
議論の要点を書き取りながら、議論の進行状況を整理していく役割です。発表の最後に向けて論点をまとめあげていくスキルが必要となります。自分が話し合いに参加しながらも、議論内容を文章化していく必要があるので、箇条書きなどを活用して構造的にまとめていくスキルが求められます。また、パソコンを使用する場合はタイピングのスキルも必要となります。
タイムキーパー
制限時間を管理し、議論が時間内に収まるよう調整する役割です。時間配分が偏らないように注意を払い、進行のペースを調整する必要があります。議論の進行状況を把握し、臨機応変に対応するスキルが必要とされます。なお、タイムキーパーは他の役割と兼務する場合があります。
監視役
メンバー同士の意見の食い違いや、議論の行き詰まりを冷静に観察しコントロールする役割です。必要に応じて、議論を中立的な方向に戻したり、新たな視点で意見することが求められます。ファシリテーターのように前面に立つのではなく、全体を支える立ち位置です。監視役は、タイムキーパーと兼務する場合が多くあります。

そるてぃーは学生時代、監視役を担うことが多かったです!監視役はうまくいけば議論の方向性を修正する立役者になるため合格率を引き上げられますが、うまく議論を誘導できなかったり発言できなかったりすると評価されないのがデメリットです。「俯瞰して見ることができる」もしくは「GDの数をこなした」方向けの役割だと言えるでしょう。
アイデアマン
議論の中で新しい視点や斬新なアイデア・発想を提案し、チームを活性化させる役割です。自分の提案だけでなく、他のメンバーのアイデアを補足して議論を深めるスキルも必要となります。
発表者
チームの結論や議論内容を発表する役割です。議論で決まった内容を簡潔かつ明確に伝えるプレゼン能力が求められます。発表の際には、議論の背景や過程も簡単に説明することで説得力を持たせることができます。
対面GDとオンラインGDの違いと注意点は?
就職活動におけるグループディスカッション(GD)は、対面形式とオンライン形式の2つに分かれ、それぞれ異なる特徴を持っています。新型コロナウイルス感染拡大を機に、ZOOMやGoogleMeetを使用したオンライン形式で参加するグループディスカッションが増えてきました。どちらの形式でも企業が評価する基準は同じですが、実施方法や必要なスキルには違いがあります。

対面のグループディスカッション(GD)
対面のグループディスカッションは、参加者が同じ空間で直接議論を行います。1グループ5〜10人、議論の時間は30〜60分程度で長くて90分で実施されることが多いです。この形式の最大の特徴は、非言語コミュニケーションがしやすい点です。表情、仕草、視線などを通じて自分の意図を補足的に伝えられるため、意思疎通がスムーズに進みます。また、直接顔を合わせることで自然な一体感が生まれ、議論が活発化しやすいのもメリットです。反面、会場への移動が必要で、交通費や時間の負担がかかることがデメリットです。対面環境では緊張感が高まりやすく、プレッシャーを感じる人も少なくありません。
オンラインのグループディスカッション(GD)
オンライングループディスカッションは、ZoomやGoogle Meetなどのツールを使い、参加者が遠隔で議論を行います。1グループ4〜6人、議論の時間は30分程度で実施されるケースが多いです。対面グループディスカッションと比べると、オンラインでのコミュニケーションの取りづらさを考慮し、やや少なめの参加人数と短めの議論時間に設定する企業が多いようです。オンライン形式の最大のメリットは、場所を問わず参加できる利便性です。特に地方学生にとっては交通費の負担がないため、選考のチャンスを増やすことが可能になります。また、オンラインであればチャット機能や録画機能を活用できるため、発言内容を補足したり、議事録をリアルタイムで共有したり、後から確認したりすることも可能です。しかし、カメラ越しでは表情や仕草などの非言語的な要素が伝わりにくく、コミュニケーションが制限される点がデメリットです。さらに、インターネット接続の不具合や技術的なトラブルが発生するリスクもあります。オンライン面接同様、事前にネット環境を整えておく必要や周辺環境の整備などを確認しておくことが重要となります。(オンライン面接については詳しく知りたい人はこちら)

対面のGDでは面接官が各グループを巡回して状況を見ていきますが、オンラインでは面接官も同じグループに入り議論の一部始終やチャットでのやりとりを随時把握していくという点も大きく違ってきます。近い距離で漏れなくしっかり評価ができるので、双方にとってもメリットが大きいと言えます。
- ルールを決める
音声や映像の乱れの影響で発言が被ってしまったり沈黙が続くことを避けるために「一回の発言は20秒以内にする」「発言したい時は画面上で見えるように手を挙げる」など予めルールを決めるとスムーズに議論を進めることができます。 - 表情や身振り手振りを大きくする
対面に比べて表情や感情が読み取りづらくなるので、身振り手振りを使って発言するように心がけましょう。 - 議事録は必ず画面共有
対面時は、紙に書いた議事録を回してみることができますがオンラインの場合だと「画面共有」やWeb会議ツールに搭載されている「ホワイトボード機能」を活用して共有する必要があります。事前にツールの利用方法などを確認しておくと良いでしょう。
どちらの形式でも、企業が評価するのは議論をリードする力、協調性、論理的思考力などです。ただし、対面形式では非言語的な印象や場の空気を読む能力が重要視される一方、オンライン形式では的確な発言や効率的な議論進行が重視される傾向があります。それぞれの特徴を理解し、事前準備を徹底することが、成功への鍵となります。
企業がグループディスカッションで評価しているポイント
企業ごとにグループディスカッションの評価基準はさまざまです。例えば、コンサルや金融業界では思考力を重視する傾向にあり、商社などではコミュニケーション能力を重視する傾向があります。なぜこのような違いがあるかというと、業界毎にビジネスモデルが異なり、また企業の特色などによっても求められる人物像も違ってくるからです。自分が受ける業界や企業がどのような人物像を求めているのかをしっかりリサーチするようにしましょう。では、評価基準はさまざまではありますが、一体どのような基準が存在しどのようなポイントを面接官は見ているのかをここで解説していきます。
【前提】共通してグループディスカッションで求められることとは?

もちろん企業によってグループディスカッションで評価するポイントは変わりますが、共通して評価されるポイントもあります。まずはGDで共通して評価されるポイントについて解説していきます。
まずは「①制限時間内に②チーム全員の脳みそを使って③より質の高いアウトプットを出すこと」がグループディスカッションにおける最大の評価ポイントと言えます。
①制限時間内にアウトプットを出すこと
1つ目はグループディスカッションで評価されるポイントとしてはグループとして制限時間内に何かしらのアウトプットを出すことが求められることです。グループディスカッションは仕事の疑似体験として行っていくもので、「納期までにアウトプットを求められる」仕事の本質を捉えた選考です。そのためどんな出来であれまずは何かしらのアウトプットが出ないとチーム全体としての評価が大幅に下がります。プロセスがどうあれ、時間内に意見をまとめて発表できるようにしておきましょう。
つまり「制限時間内にアウトプットを出すことに対して貢献ができるか」が見られています。ですので適切な時間の管理や議論の進め方などに対して発言を積極的に行うことが評価に繋がります。
②チーム全員の脳みそを使うこと
2つ目はチーム全員の意見を活用してアウトプットを出すことです。これも仕事の疑似体験としての考え方になりますが、せっかくチームでアウトプットを出すことを求められているのでチームメンバーそれぞれの意見や考え方を集約することがよりよいアウトプットに繋がります。
つまり「チーム全員の意見を聞き出すこと」や「チームメンバーの意見を集約すること」に対して貢献できるような発言や行動が見られています。
③質の高いアウトプットを出すこと
最後は質の高いアウトプットを出すことです。もちろん仕事ではより質の高いアウトプットを出すことが求められます。ですのでよりテーマに沿ったクリティカルなアウトプット出すことができるかが非常に重要です。つまり、よりテーマの本質に近い議論に導く意見を出せたり、方向性を見出すことができる人がより評価されるのです。
人間力(人間性)
ここでいう「人間力」というのは、TPOを考えた行動がとれるか・最低限のマナーを理解できているか・清潔感を意識できているかどうかなどを中心に判断しています。もちろん性格特性についても判断されますが、評価は性格の良し悪しではなく「企業とマッチしているかどうか」という点を判断されています。性格特性とは、個人が持つ一貫した行動や思考、感情のパターンを指します。これは、性格を構成する要素のことであり、「外向的」「内向的」「協調性が高い」「慎重」など、さまざまな特性が存在します。例えば営業要素の強い企業や業界であれば外交的な人の方がマッチしますし、エンジニアのような職種であれば内向的な人の方が適していたりします。外交的・内向的のようなマッチングが重要な性格特性もありますが、「素直な人」「気が使える人」「明るい人」などの性格特性が好まれる場合もあります。一方、「攻撃性が高い人」「怒りの沸点が低い人」「自己肯定感が高すぎる/低すぎる人」などは企業からは嫌煙されやすいので注意しましょう。
コミュニケーション能力
グループディスカッションにおいてコミュニケーション能力は非常に重要です。前述したとおり、チームとしてより良いアウトプットを出すためにはチームメンバーを巻き込んだ議論を行う必要があります。より良いアウトプットを出すためにチームメンバーとの信頼関係を築いたり、ファシリテーションしたり、意見を聞き出したりすることが求められます。ここでいうコミュニケーション能力は「明るい、関係値をつくれる」という意味ではなく「目的を達成するために必要なものを獲得するために行動ができること」です。コミュニケーション能力は社会人基礎能力としても非常に重要な能力ですので必ずアピールできようにしましょう。
論理的思考力
より質の高いアウトプットを導き出すためには適切な目標・課題設定と施策の策定、検証が必要です。また課題に対してマッチしている施策を考えることができているかという点も非常に重要です。質の高いアウトプット=納得感のあるアウトプットですので、論理的に整理されたアウトプットであればあるほど評価しやすくなります。論理的に物事を考えられると、構造的に自称を整理することができ、問題解決に繋がるため成果を上げることができるようになります。
問題解決力
問題解決能力とは「発生した問題の原因を分析して解決策を考え、実行する能力」を指します。こちらもより質の高いアウトプットを出す観点になりますが、より本質的な問題を特定し原因となる課題を考えることができるかどうかがアウトプットの質を大きく左右します。根本で解決すべき問題を見極めることができる能力はグループディスカッションにおいても重宝されます。
リーダーシップ
前述したコミュニケーション能力と親しいですが、チームとしての議論を勧めていく上ではリーダーシップが必要となるケースがあります。最終的な意思決定や意見の集約などの観点で必要とされますのであるとなお良いでしょう。リーダーシップは「チームを引っ張る」という意味合いが強いですが、ただ熱量で引っ張るだけでなく「適切な方向にチームの議論を導くこと」もリーダーシップと言えます。みなさんなりのリーダーシップをアピールしましょう。
協調性とチームワーク
グループディスカッションでは意見が割れたり合わないというケースも少なくありません。その中で協調性を持って共通の目的に向かって議論ができるかや、チームワークを持って議論を進められるかが非常に重要です。営業職であってもチームで仕事を行うケースは必ずあります。組織に入る上では協調性は求められるため、この点もアピールできるようにしましょう。
積極性
大前提ではありますが、意見を発することができなければ評価されることはありません。まずは自分の考えをチームメンバーにシェアをしないと何も始まらないため、まずは臆せずに自分の意見を発言して評価の土台に上がりましょう。
グループディスカッションで落ちる理由と注意するポイント
ここまで企業視点でどういった点を評価しているかを解説しました。では落ちる理由には具体的にどういった理由があるのでしょうか。落ちる理由と対処法を解説するので、自分の立ち回りを振り返りながら確認してみましょう。
相手の意見を否定してしまう
意見を否定ばかりしてしまうと協調性がないと判断されてしまいかねません。「議論」となると意見をぶつけ合わなくてはいけないと思いがちですが、グループディスカッションは勝ち負けを争うものではありません。議論する場合は相手の発言を否定するのではなく、相手の意見を元に前向きな意見の発言や違う視点での提案に置き換えて発言するようにしましょう。
多数決で意思決定してしまう
多数決で物事を決めてしまうと「全員の脳みそを使ってアウトプットする」事ができてないことになってしまいます。時間が迫ってきた場合どうしても多数決で決めたくなってしまいますが、なるべく話し合いを通じて合意形成できた状態で終了できるようにしましょう。グループディスカッションは「時間内に参加者の納得感と合意形成を得た上で、選考官にとっても納得感ある答えを導き出すこと」が重要となるので、無理矢理議論をまとめないように注意しましょう。
議論の本質から逸らすクラッシャーになってしまう
グループディスカッションにおけるクラッシャーとは「議論を妨げる人」のことを指します。「自己主張が激しく否定的」「全く発言をしない」など様々なタイプがいますが、進行を妨げ場を乱す存在はすべてクラッシャーと言えます。クラッシャーがいることで議論がスムーズに進まず、また意見を否定されることでメンバー全体の士気が下がりチーム全体に悪影響を及ぼしてしまいます。評価においても、クラッシャーのみならずチーム全員が選考に落ちてしまう可能性もあります。クラッシャーは意図的に議論の邪魔をしている場合もありますが、多くの場合、自分がクラッシャーになっていることに気づいていません。自分が以下の点に当てはまっていないか、客観視してみましょう。
- 自己主張が強い|自分の意見が正しいと思い込んでる
周りのメンバーに説得されても自分の意見を曲げず、自分の意見を貫き通していませんか?
意見をすることは大事ですが、自分の意見が全て正しいわけではありません。相手の考えも受け入れられる柔軟性を持っていきましょう。 - 相手の意見を否定する
自分の意見を言わずに、人の意見に対して批判だけしていませんか?
他のメンバーが萎縮して発言できない環境を作らないように注意しましょう。 - 全く発言しない
意見を求められているのに、何も発言せず黙ってしまってはいませんか?
発言をしない人がいる状況で議論を進めてしまうと、企業側に「話せていない人がいるのに気にせず進めてしまうグループである」と判断されてしまいます。
※クラッシャーへの対処法※
クラッシャーの行動に対して感情的にならないことが最優先です。冷静に対応することで、他の参加者や採用担当者から、落ち着いた判断力を持つ人だと評価されます。では、どのように対処すれば良いのでしょうか?クラッシャーのタイプごとに対策方法は変わってきます。
- 自己主張が強いタイプ
自己主張が強いタイプのクラッシャーは自分の意見が正しいと思い込んでいるため、相手の発言を完全に否定せず一旦受け入れ、相手の意見を褒めた上で「この観点で考えた場合はどう思うか」など議論を軌道できるような聞き方で相手の意見を引き出すことがポイントです。 - 相手の意見を否定するタイプ
相手の意見を否定するタイプのクラッシャーは、自分の意見を言わずに否定のみする傾向があります。そんなクラッシャーには、批判に対して「なぜそう思うのか」「あなたはどうしたら良いと思うのか」と批判に対して深掘りをしてみましょう。深掘りをすることで、闇雲に批判することをやめたり、自分の意見を出すようになるでしょう。 - 全く発言しないタイプ
発言をしないタイプのクラッシャーは、わざと沈黙しているパターンと発言するのが怖くてできないタイプに分かれます。相手を指名して発言を促すようにしたり、YESかNOで答えられるような質問を投げかけるなどの工夫をすると良いでしょう。
クラッシャーが話を独占したり、議論を混乱させたりしている場合、「皆さんの意見を整理すると、〇〇の点については一致していますね。次は××について話しましょう。」など、議論の進行役として全体を整理するのも効果的です。

クラッシャーがあまりにも議論を混乱させ、状況をコントロールできない場合は、無理に対処しようとせず、自分の役割を全うすることも一つの選択です。採用担当者は、そうした困難な状況での各参加者の対応力や冷静さをしっかりと評価してくれるので慌てないようにしましょう!
グループディスカッションの5つの型とテーマ例
| 5つの型 | 特徴 | 判断される脳力 |
|---|---|---|
| 自由討論型 | ・与えられたテーマについて自由に議論する形式。 ・答えに正解のないテーマについて討論する。 例: | 論理的思考力 積極性 協調性 |
| 課題解決型 | ・実際のビジネス課題や社会問題に対して解決策を議論する形式。 ・ある課題を解決するためのアプローチ方法を考える。 例:「少子化対策を提案しなさい」や「地方創生をテーマにした新規ビジネスを考えなさい」。 | 論理的思考力 問題解決力 発想力 |
| 選択型 | ・複数の選択肢から最適なものを選び、その理由を議論する形式。 例:「A社とB社、どちらに投資すべきか」「新商品のターゲット層は20代か30代か」。 | 言語化能力 協調力 柔軟性 |
| フェルミ推定型 | ・数字に基づいた議論を行い、論理的な結論を導き出す形式。 例:「日本にあるコンビニの総数を推定せよ」や「1日に販売されるピザの数を推定せよ」。 | 応用力 論理的思考力 数字に基づく仮説構築力 |
| ディベート型 | ・賛成派と反対派に分かれて、あるテーマについて論戦を行う形式。 例:「リモートワークは常態化すべきか」「消費税を増税すべきか」 | 論理的な主張力 説得力・提案力 共感性 |
自由討論型
与えられたテーマについて自由に議論する形式です。答えに正解のないテーマについて討論することが多いことが特徴です。積極的に発言する姿や、結論を導き出すまでの進行力(協調性など)を判断しています。答えに正解がないからこそ、意見がまとまりにくいのでその過程をよく観察されています。
課題解決型
実際のビジネス課題や社会問題に対して解決策を議論する形式です。ある課題を解決するためのアプローチ方法を考えるようなテーマで出題されます。現状と理想を明確にしその乖離を整理し、実現可能な解決策を見つける力を観察されています。
選択型
選択型はチームで正解のない2択から一方を選び、選択した理由を明確に話すことが重要です。そのため様々な観点で2つの選択肢を比較できているかや、どのような評価項目を持ってチームとして合意形成しているかなどを評価しています。そのため合意形成にインパクトを与えるファシリテーションや発言、また比較すべき項目のアイデアを出せると人事に評価されやすいでしょう。
フェルミ推定型
一般的にはコンサルティング企業にて多用されるもので、その他のテーマに比べてある程度の正解が決まっており様々な仮説を立てながら可能な限り正解に近い答えを導き出すことが求められます。フェルミ推定型のGDを攻略するためには様々なデータを頭に入れておくことが重要です。
- 日本人口:1億2,000万人
- 日本の世帯数:5,000万世帯
- 日本のサラリーマン平均給与:400万円
- 日本の企業数:400万社
- 国土面積:38万平方キロメートル (30%平地、70%山岳地)
- 日本の平均寿命:80歳
- 世界の人口:70億人
ディベート(討論)型
ディベート型は別グループと討論形式で意見をぶつけ、より納得度の高い意見を主張できた方がより評価される内容になります。特に「相手がどのような根拠で主張してくるか」の仮設立てをしながら自チームの主張をすることでカウンタートークを用意することができます。もちろんチームとして良い意見を出せることも重要ですが、その意見をまとめるにあたってみなさんがどのようないい影響を与えたのかが合格には何よりも重要です。
グループディスカッションの練習方法
ここまでグループディスカッションの基本の流れと型について解説しましたが、頭で理解できていても実践となるとちゃんと知識を発揮できるのか不安ですよね。グループディスカッションも面接同様、練習が大事になります。グループディスカッションの体験ができるイベントに参加したり、グループディスカッションの選考がある企業の選考を受けてみたりと、場数を踏むことが大事になります。ここでは一人でできる練習方法やイベントに参加するメリットについて解説していきます。
動画を撮って客観視する
自分でテーマを考え話す姿を動画に撮り、話し方・表情・言葉遣い・態度を客観視してみましょう。自分の意見を伝えるときに表情が固かったり、早口になってしまうと威圧感があると捉えられる場合もあります。動画を振り返ってみて、直すべき点は繰り返し意識して練習していきましょう。
ニュースを見て自分の意見を持つようにする
グループディスカッションは自分の意見を伝える場です。日頃から、物事に対して疑問を持ち自分なりの意見や考えを持てるよう練習しておく必要があります。例えば、「AIの発展が社会に与える影響」など、関心のあるテーマに対して賛成・反対の立場を考え、根拠を挙げて理由を述べる練習がおすすめです。練習の一環として、自分の意見を文章化する習慣をつけることも良いでしょう。「なぜそう思うのか」「その結論に至った根拠は何か」を明確にすることで、論理的な発言ができるようになります。ノートや動画に自分の意見をまとめて発表する練習をしていきましょう。
複数人で練習できる場を探す
インターンシップやグループディスカッションのイベントに参加するのもおすすめです。他大学の学生や社会人と議論することで、多様な価値観や考え方に触れることができ、自分の意見の伝え方や議論の進行方法を客観的に見直すきっかけになります。フィードバックをもらえるイベントに参加して、第三者からの意見をもとにブラッシュアップしたり、自分に合った役割はどれなのかを実際に体験してみて見極めていくと良いでしょう。グループディスカッションは何よりも「場数を踏む」ことが勝つための鍵となります。いきなり本番を迎えるのではなく、何度も実践練習ができるイベントへ足を運び経験値を増やしていきましょう!
選考・インターン前日や当日に不安になったときは、じぶんぽっくで紹介されている対処法がおすすめです。
【厳選】GD対策イベント3選
では実際にグループディスカッションができるイベントとはどのようなものがあるのでしょうか?1日で実践練習がしっかりとでき、フィードバックや特別オファーがもらえるおすすめのイベント3選をご紹介いたします。
ジョブトラ

【就活生10万人以上が参加した早期内定の登竜門】と呼ばれるジョブトラは、自己分析や企業分析など、内定獲得までの就活ステップの基礎を学びながら本選考ワークを体験できる総合型の就活イベントです。大手企業のインターンや本選考で取り入れられている難解なビジネスゲームを実践できるのが他にはない特徴です。7社程度の参加企業から、学歴やガクチカ関係なく当日のワークの言動で評価された場合は、特別選考スカウトを受けることができます。
- 【就活生10万人以上が参加した早期内定の登竜門】
- ビジネスゲームでインターンシップのプチ体験が出来る
- 学歴やガクチカ関係なく、イベント当日の言動だけで特別スカウトがもらえる
- 少人数の座談会で企業の人事と会える
DyDo、世田谷自然食品、デジタルホールディングス(オプト)、TRYグループ、PERSOLなど
伊藤忠商事、三菱商事、味の素、サントリーホールディングス、トヨタ自動車、パナソニック、花王、損害保険ジャパン、ファーストリテイリング、日清食品、ブリヂストン、キリンビール、東京海上日動火災保険、電通、博報堂、グーグル、楽天グループ、アクセンチュア、KDDI、パソナ、ディー・エヌ・エー、NTTドコモ、三井住友銀行、住友生命保険、野村證券など
グループディスカッションは「場数を踏む」ことで勝てる!!
今回はグループディスカッションで評価されるポイントと練習方法、場数を踏むためのイベントについて解説しました。学生のみなさんにとってグループディスカッションは異質なものと捉えられがちですが、場数を踏むことで「日常」にすることができます。グループディスカッションを日常にし、いつも通りのパフォーマンスを発揮できるようにすれば自ずと評価されるようになります。この記事を参考に対策イベントに参加してGDの練習をし、GDが得意になれるように頑張っていきましょう。