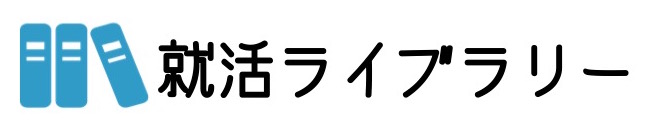大学卒業後の進路として、「就職」を選ぶか、それとも「大学院進学」を選ぶか。これは多くの学部生が直面する、人生の大きな岐路の一つです。どちらの道にもそれぞれの価値があり、一概にどちらが「正解」ということはありません。大切なのは、あなた自身の価値観、目標、そして状況に照らし合わせて、納得のいく選択をすることです。
この決断が難しいと感じるのは、あなただけではありません。実際、多くの最終学年の学生が、卒業後の具体的なステップについて決めかねているという調査結果もあります “。この感覚はごく自然なものです。この記事では、あなたがこの重要な選択肢を冷静に検討し、それぞれのメリット・デメリットを理解し、最終的に自分らしい道を見つけるための考え方や情報収集の方法を整理していきます。これは問題ではなく、あなたの未来を形作るための重要な探求の機会なのです。
この選択の背景には、学部教育で得られる広範な知識と、特定のキャリアパスで求められる専門性や、より深い知識への探求心との間にギャップが存在する可能性も考えられます。学部での学びが、目指す道にとっての終着点なのか、それとも更なるステップへの準備段階なのか、この問いに向き合うことが求められます。また、この決断には、「自分は学生なのか、社会人なのか」というアイデンティティの変化、友人との比較、家族からの期待といった、感情的な側面も深く関わっています。単なる論理的な比較だけでなく、こうした心の動きにも目を向けることが、後悔しない選択をする上で重要になります。
大学院進学と就職を悩むシチュエーション
①就職活動がうまく行かず、大学院進学を考えている
大学3年から就職活動を行い頑張って就職活動をしてきたものの、思うような企業から内定が出ず苦戦すると「就職活動」に対してネガティブな印象を持ってしまいます。すると目の前の就職活動から逃げ出したくなり、大学院への進学をすることで意思決定を先延ばしにすることができるのではないかと考えしまうことがあります。
②大学院進学を考えていたが、周りが内定を獲得しこのままでいいか不安になった
明確に学びたいことややりたいことが有り大学院進学を前提に考えていたが、学部就職する周りの友人がスムーズに内定を獲得していく中で「自分は穏当にこのままでい良いのか?」と不安になってしまうことがあります。
③これから進路を考える上で、大学院進学と就職のメリットデメリットを知りたい
これから自分の将来を考える中で、「これから自分にどんな選択肢があるのか?」大学院進学と就職のメリット・デメリットを知りたいと考えるでしょう。
なぜ大学院進学と就職で悩むのか?
卒業後の進路選択がこれほどまでに悩ましいのはなぜでしょうか。いくつかの共通する理由が考えられます。
就職活動は情報戦が故に情報が錯綜している
まず、情報の過多が挙げられます。周囲からのアドバイスは様々で、時には矛盾していることもあります。将来のキャリアパスは不透明に見え、数年後の社会や経済がどうなっているか予測することも困難です。
次に、一方の道を選ぶことでもう一方の道で得られたかもしれないチャンスを逃してしまうのではないか、という不安を感じることがあります。
キャリアについて考えるタイミングが遅い
また、自分自身の目標が明確でないことも、決断を難しくします。自分が仕事や人生に何を求めているのか、どんな価値観を大切にしたいのかがはっきりしないと、どちらの道が自分に合っているのか判断できません。
就職しなければいけないというプレッシャー
経済的なプレッシャーも無視できません。奨学金の返済や経済的自立への願望がある一方で、大学院進学にはさらなる学費や生活費がかかります。例えば、近年の学生が抱える平均的な負債額を考えると、追加の学費負担は大きな懸念材料となり得ます。
そして、「この選択が自分の人生を決定づけてしまうのではないか」という決定の重圧感。実際にはキャリアパスは後から変更することも可能ですが、この時点では非常に重大な、後戻りできない選択のように感じられることが多いのです。多くの学生が「間違った選択をしてしまうことへの恐れ」や「将来の仕事の見通しへの不安」を抱えているという声もあります。
就職活動が「人生で一度の、人生を決める選択」だという認識
また今あなたは不確実な未来に対して最適な選択をしようとしていませんか?学生は、比較的よく知っている現在の「学生生活」と、まだ完全には理解できていない二つの未来、「社会人生活」と「大学院生生活」を比較検討しなければなりません。これには将来の自分の満足度、キャリアの進展、市場の動向などを予測する必要がありますが、それは本質的に困難です。だからこそ、未来を完璧に予測しようとするのではなく、現在の自己理解と価値観に基づいて「正解にしたいと思える決断ができるか」焦点を当てるべきなのです。
さらに言えば、この「選択の悩み」自体が、学部時代におけるキャリアプランの設計や自己分析が不足していたことの表れである可能性もあります。もしみなさんがまだ実際に働くイメージが付いていなかったり、自身のスキル、興味、価値観をキャリアという文脈で深く考えていなかったりすれば、卒業間近になって「どちらを選べばいいかわからない」という状況に陥りやすくなります。この決断の時期は、そうした自己分析を強制する機会ではありますが、本来はもっと早い段階から始めるべきプロセスなのです。
大学院進学のメリット
学部卒業後、続けて大学院へ進学する道には、どのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。
メリット①:•高い専門性を習得し、専門職へ
大学院では、学部よりも深く特定の学問分野を掘り下げることができます。もし明確に学びたい分野が決まっていたり、継続して研究したい方、また研究内容を生かして就職をしたいという方は大学院進学がおすすめです。特に理系の研究職や開発職などでは、修士以上の学歴が応募の必須条件となっている企業が少なくありません。また、法科大学院修了による司法試験受験資格や、教員専修免許状の取得など、特定の資格取得に繋がる場合もあります。専門性の高い職種を目指すのであれば、大きなアドバンテージとなります。
メリット②:初任給と生涯年収の高さ
多くの企業で、大学院修了者の初任給は学部卒者よりも高く設定されています。厚生労働省の調査でも、平均賃金において院卒者が学部卒者を上回る傾向が見られます。学部卒のほうが早期に就職して働き始めるため一時的には学部卒より生涯賃金が少ない傾向にありますが、定年までのことを考えれば大学院卒のほうが生涯賃金は5000万円ほど高くなります。
| 学歴 | 初任給(月給平均) | 生涯年収(平均) |
|---|---|---|
| 大学院卒 | ¥276,000 | 約 2.5〜2.8億円 |
| 学部卒 | ¥237,300 | 約 3.0〜3.3億円 |
| 差額 | ¥38,700 | 約5000万円 |
ユースフル労働統計 2022:https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/kako/2022/documents/useful2022_21_p316-361.pdf
メリット③:学校推薦を使って就職を目指せるケースも
学や教授からの推薦枠は、研究実績のある大学院生が優先されることが多く、教授がコネクションを持っている企業への推薦枠を勝ち取るチャンスが生まれます。そうすると必然的に大手企業や研究環境の整った企業で働けるチャンスを手にすることができます。大手企業などは非常に倍率も高いため、通常ルートで採用されるのは至難の業です。学校推薦をうまく使えは他の学生と競争することなく内定を勝ち取ることができる可能性が高まるのです。
大学院進学のデメリット
デメリット①:経済的負担
大学院進学には学部よりも高額な学費が必要となります。より深く研究していくにあたって必要な資料や機材などがあるため、学費も相対的に高くなる傾向にあります。学部での学費よりもおおよそ50万円ほど高いと言われていますので、経済的な負担もそれだけ大きくなります。またこれまで学費を自分のバイト代で賄ってきた方も、大学院に進学すると研究活動で多忙になりアルバイトを十分にできず卒業ができないというケースも発生していますので注意が必要です。
デメリット②:大学院で学んだ専門性が就職で活かせない(特に文系)
大学院で深く学んだ研究についても、必ずしも就職で活かせるとは限りません。特に文系の大学院の場合、学んだ内容を業務で活かすことができないケースが散見されます。例えば文学系の修士課程で学んだ場合、教師や教授などであれば活かせるものの、それ以外で直接的に知識を生かして働くお仕事にはかなり限りがあります。大学院で学んだからといって、必ずその専門性を生かせる仕事があるとは限りません。これから学ぶ内容が実務で活かせるものなのかは確認が必要です。
デメリット③:研究と就活の両立の難しさ
大学院生は非常に忙しいです。大学院での講義だけでなく自身の研究や研究室内での庶務(研究室の取りまとめや雑務など)、アルバイトなどがあります。またそれに加えて就職活動という非常に大きなタスクが降り掛かってきます。学部生の場合、多くの単位を取得した状態で就職活動を行うのに対し、大学院生は講義と研究と修士論文、そして就職活動を全て並行して行う必要があるのです。
- 特定の学問分野に対する強い情熱があり、深く探求したい、研究したいという意欲がある人
- 目指す職業に専門職があり、その職業が修士号や博士号が明確に必要とされている人
- 奨学金やRA/TAなどで学費・生活費の目処が立っている、あるいは明確な資金計画がある人
- 体系的な学習や研究活動といった、学術的な環境で能力を発揮できる人
学部就職するメリット
学部卒業後すぐに社会に出ることを選んだ場合、どのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。
メリット①:経済的自立
学部就職をするということは卒業後すぐに給与を得て、貯蓄や投資を始め、自分自身の経済を管理できるようになります。そうすると、今仮にご両親の仕送りやサポートがあって生活をしている状況を脱却し親に頼らず自分が稼いだお金で生活をしていくことができます。例えば現在実家暮らしでも一人暮らしができるようになったりします。また大学進学にかかる費用は非常に膨大ですので、すでに奨学金を借りている方は大学院進学せずに就職することで2年間も早く奨学金を返済し始めることができます。月々の支払額を減らしたり、早めの完済を目指すことも可能になるでしょう。
メリット②:早くから社会人経験ができスキルアップに繋がる
大学院に進学する同級生よりも2年早く社会に出て、実務経験を積むことができます。OJT(On-the-Job Training)などを通じて、ビジネスの現場で通用する実践的なスキルや知識を早期に習得し、成長スピードを加速させることが可能です。この2年間の経験は、その後のキャリア形成において大きなアドバンテージとなり得ます。
メリット③:ポテンシャル採用として専門外の業界に挑戦できる
日本の新卒採用は世界的に非常に稀ですが、大卒採用をポテンシャル採用として扱うケースが一般的です。大学院進学ともなれば企業側としては専門的な知識を活かせる人材を採用する意識が強くなるものの、学部卒の場合はこれまで学んだことのない業界や職種であっても新卒としての伸びしろ(ポテンシャル)があれば採用をしてくれます。そのため、大学院進学してから就職するよりも学部卒就職したほうがポテンシャル採用として評価してもらえる可能性は高くなると言えます。
学部就職するデメリット
デメリット①:専門職に就職できる可能性が低い
上述したように学部就職はポテンシャル採用を行っているため、募集している求人は専門職ではなく総合職よりの求人が多くなる傾向にあります。そのため営業職や事務職などの求人が多くを占めます。例えば理系分野の研究開発職などは修士課程の卒業予定者しか応募できないなどの制限があるケースが多いため、高度な専門職に就きたい場合には大学院進学をしておくほうが選択肢が広がります。
デメリット②:初任給や生涯年収が相対的に低い
上述したように大学院進学した上で就職した場合に比べて、学部就職した場合は初任給や生涯年収が相対的に低くなっています。ただし大学院進学した学生は就職しないので、最初の数年間は学部卒の学生の方がトータルの収入は多くなります。
デメリット③:(理系の場合)学校推薦を使えない
こちらも上述しましたが、理系学生の場合は学校推薦という方法で就職するルートがあります。ただこの学校推薦は大学院卒の学生が優先となるため、学部就職を目指す場合学校推薦を使って就職することは難しいと考えるべきでしょう。
- 現時点で、就職したい業界や職種がある程度明確な人
- 経済的な自立や、実践的なスキル・経験の獲得を優先したい人
- 現時点では、特定の学問分野を深く掘り下げたいという強い動機がまだない人
- 座学よりも、実際にやってみる中で学ぶ方が得意な人
ここで重要なのは、「早く就職すること」が正解ではないということです。単に「就職した」という事実だけでなく、その仕事が自身の長期的な目標に関連するスキルや知識を提供してくれるか、成長の機会があるか、良い指導やメンターシップを受けられる環境か、といった点を吟味する必要があります。目標に繋がらない経験や、成長が見込めない環境での経験は、必ずしもプラスになるとは限りません。
一方で、すぐに就職することが、将来の大学院進学の道を閉ざすわけでは決してありません。むしろ、社会人経験は、大学院での研究テーマをより明確にし、学習意欲を高め、経済的な基盤を提供し、さらには入学選考においても高く評価される要因となり得ます。多くの大学院では、社会人経験を持つ学生を積極的に受け入れていますし、働きながら学べるパートタイムのプログラムも存在します。したがって、即時就職は、終着点ではなく、将来の更なる学びへの回り道やステップと捉えることも可能なのです。
大学院進学or就職?採用責任者の本音
「逃げ」の大学院進学は、結局自分を苦しめる
一番にお伝えしたいのは、「ネガティブな理由で大学院進学」を考えている人は今すぐ就職活動を行ってください。大学院進学をする目的が「学びたい、成長したい」ではなく「就活を休みたい」「意思決定を先延ばしにしたい」という理由の場合、大学院進学下としても絶対にうまくいきません。
また大学院進学したあとに就職活動を行う上でもリスクはあります。修士として就職活動するということは学部卒の学生よりも2歳も歳を重ねているため、若さ、フレッシュさを求める新卒採用においてはディスアドバンテージになります。2歳の年令を重ねているだけのスキルや採用するメリットがないと企業は学部卒の学生を採用したいはずです。つまり大学院進学したあとの就職は採用ハードルが高くなるのです。
学部就職のメリット「ポテンシャル採用」はチャンス
日本の新卒採用、特に学部卒採用は、世界的に見ても非常にユニークな「ポテンシャル採用」が主流です。これは、現時点でのスキルや知識よりも、入社後の成長可能性や学習意欲、人柄、コミュニケーション能力といった「伸びしろ」を重視する採用方式です。企業側も、新入社員を一から育てる体制を整えていることが多いです。
これは、現時点で多少自信がなかったり、就職活動で苦戦していたりする君にとって、大きなチャンスなのです。たとえ面接でうまく話せなくても、グループディスカッションで目立てなくても、君の中に秘められた真面目さや、困難な状況でも諦めずに努力する姿勢、素直さ、学びへの意欲などが伝われば、企業は君の将来性に賭けてくれる可能性があります。
しかし、大学院に進学し、2年後に就職活動を再開する場合、企業側は学部卒と同じようなポテンシャルだけでなく、大学院で培った専門性や研究成果、より高度な論理的思考力などを期待するようになります。つまり、評価のハードルが上がるのです。
今、この学部卒というタイミングだからこそ受けられる「ポテンシャル採用」の恩恵を、最大限に活用すべきだと私は考えます。
社会人経験は何よりの成長エキス
もちろん、大学院での研究活動も人を成長させます。しかし、ビジネスの現場で多様な価値観を持つ人々と協働し、目標達成に向けて試行錯誤し、時には理不尽な要求や困難に直面しながらも乗り越えていく経験は、学問の世界だけでは得難い、実践的な成長をもたらします。
コミュニケーション能力、問題解決能力、交渉力、タイムマネジメント能力、プレッシャーへの耐性…。これらは、座学だけでは身につかない、いわゆる「社会人基礎力」であり、実際に仕事を通して揉まれる中で磨かれていくものです。
早く社会に出てこれらの経験を積むことは、君の視野を広げ、人間的な深みを増し、将来のキャリアの選択肢を豊かにします。たとえ最初に就職した会社が自分に合わなかったとしても、そこで得た経験やスキルは決して無駄にはなりません。むしろ、それが次のステップに進むための貴重な糧となります。
就職活動のスタートが遅れ、ズボラな性格もあって後手に回ってしまったと感じている君だからこそ、早く社会に出て、仕事を通じて「やらざるを得ない」環境に身を置くことが、自己変革の大きなきっかけになる可能性も秘めています。
就活の劣等感はアクションと成果でしか解消されない
周りが内定を得ていく中で、自分だけが取り残されているように感じる劣等感は、非常につらいものです。その気持ちから逃れたい一心で、大学院という「別の道」に進むことで一時的に安心感を得ようとする心理も理解できます。
しかし、残念ながら、進路を変えただけでは、その劣等感が根本的に解消されることは少ないです。むしろ、2年後に再び同じような状況に陥ったり、「自分は結局、学部卒で就職できなかった」という新たなコンプレックスを抱えてしまったりする可能性もあります。
劣等感を乗り越える一番の方法は、やはり、今直面している困難から逃げずに立ち向かい、たとえ小さな一歩でも「行動」を起こし、結果を出すことです。内定を得るという目標に向かって、諦めずに努力を続けるプロセスそのものが、君の自信を取り戻す力になります。「自分は困難な状況でも、最後までやり遂げた」という経験は、将来どんな壁にぶつかった時でも、君を支える強い土台となるでしょう。
自己分析と選択肢の比較検討を進めたら、次は外部からの情報を集め、信頼できる人々に相談することで、考えを深め、決断を確かなものにしていきましょう。
大学院進学か就職か迷った時のチェックリスト
キャリア選択に迷っている方はこのチェックリストを参考にしてください。すべての項目で「明確にYES」といえない場合は就職を選ぶべきです。大学院進学を選択する際は明確な目的と意図を持って意思決定しましょう。
- 明確な研究テーマと目的意識がありますか?
- 大学院で何を学び、どんな研究をしたいのか、具体的なテーマや問いがあるか
- それは、学部での学びを深めたいという純粋な知的好奇心に基づいているか
- その研究は、本当に大学院でしかできないことですか?
- 企業の研究開発部門や、研究所などで働きながら学ぶという選択肢はないのか
- 指導を受けたい教員はいますか? その研究室の雰囲気は自分に合っていますか?
- 事前に研究室訪問をしたり、院生に研究内容や指導方針、雰囲気などを確認する
- 2年間の学費と生活費を賄う具体的な計画はありますか?
- 学費免除や奨学金制度について調べたか
- 親からの援助があるか、アルバイトをする時間は確保できるか
- 大学院修了後のキャリアプランを具体的に描けていますか?
- 修士号を取得することで、どのような職に就きたいですか?
- その職種では、修士号が有利に働く、あるいは必須ですか?
- 研究活動の厳しさや孤独に耐えられる覚悟はありますか?
- 地道な研究をする粘り強さ、自律性、計画性はあるか
- 研究が進まないストレスや、孤独感にどう向き合うか
これから就職活動を始める方への注意点
就職活動を始める/終える時期は重要ではない
まず前提としては就職活動はいつ始めるか、いつ終えるかは全く重要では有りません。大事なことは「正解にしたいと思える意思決定ができるか」が重要です。自分自身が納得できるキャリア選択のために、自己理解や業界・企業理解に全力を注ぎましょう。「正解にしたいと思える会社」に入ることが就職活動におけるゴールです。そのための努力は惜しまずに就職活動に取り組みましょう。
効率的に就職活動を行うべし
とはいえ新卒という魔法のチケットを使って就職活動ができる期間には限りがあります。そのためいかに効率的に自己理解、業界研究、選考対策を進められるかが何よりも重要です。より効率的に就職活動を進める事ができるツールは積極的に活用していきましょう。
効率的な就職活動を行うために活用すべき就職支援サービス
最速で内定獲得を目指すならジール就職エージェント

| 求人数: | ★★★★★ |
|---|---|
| コンテンツの充実度: | ★★★★ |
| 内定までの期間: | ★★★★★ |
| 人事評価: | ★★★★ |
ジール就職エージェントを運営する株式会社ジールコミュニケーションズは、採用・就職支援事業に力を入れている企業のため、3,000社以上の企業の採用と30,000名以上の学生の就職支援を行なってきた実績とノウハウがあります。厳選された優良企業3,000社から自分に合った企業の紹介が可能。最大の特徴としては、大手ナビサイトには掲載されていない求人の紹介を受けることができる点です。また、中には最短2週間で内定を獲得できる企業の紹介もあります。メーカー・商社・広告・IT・人材・住宅・建設・コンサルなど、様々な業界の企業の求人を持っているので、「希望業界が決まっていない学生」でも面談を通じて自分に合った業界や企業を見つけることができます。
- 最短2週間で内定!
- 面談は最短当日も可能。オンライン・オフライン自分にあった面談形式を選択できる!
- 3,000社以上の求人から自分にあった企業を提案してもらえる
みずほ証券/伊藤園/タカラトミー/青山商事株式会社/長谷工グループ/DyDo/ノバレーゼ/ミキハウス/湘南ゼミナールなど

「自分でも就活を進めながらエージェントを利用したい」「大手ナビサイト以外の求人を知りたい」学生にぴったりの就職エージェントです!
ジール就職エージェントで紹介する企業のほとんどが、大手ナビサイトに掲載されていない独自の優良求人のため、自身でエントリーした求人と並行して利用することで効率よく就職活動を進めることができます。就職エージェントの利用を検討している学生の中でも「エージェントを使ってみたいけど自分でも就職活動を頑張りたい」そう思っている学生も多いのではないでしょうか。ジール就職エージェントを使うことで、バランスよく就職活動を進められるので非常におすすめです!
大手企業運営の安心感で選ぶならdoda新卒エージェント

doda新卒エージェントは、株式会社ベネッセ i-キャリア(ベネッセグループ)が運営する完全無料の新卒向けの就活エージェントです。2024年卒の登録学生数はなんと140,000名以上!
サービスの特徴としては、契約企業が6,500社以上(※)あり、ナビサイトでは見つけられない企業に出会うことが可能。プロのキャリアアドバイザーは国家資格を保有したプロフェッショナルが複数在籍しており、面談を通じて自分に合った企業を厳選して紹介してくれます。エリアや文理ごとに専任のキャリアアドバイザーが担当してくれるも魅力の一つです!紹介する求人の中には、ES不要や一次面接免除のdoda新卒エージェント独占の選考・ルートがあります。過去利用者の中には最速2週間で内定獲得した人も!価値観にフィットするだけでなく、強みや適性を活かして入社後に活躍できそうな企業を紹介してくれるので、サービスが気になった人は相談してみましょう!
- 2024年卒の登録学生数は140,000名以上!
- 契約企業が6,500社以上(※)あり、ナビサイトでは見つけられない企業に出会える
- プロのキャリアアドバイザーは国家資格を保有したプロフェッショナルが複数在籍
- doda新卒エージェント独占の選考・ルートあり!
*当該サービスにお申し込みいただいた法人の累計(2024年3月時点)
パナソニックグループのIT事業会社/SONYグループのIT・通信中核企業/三井金属グループの中核会社などの大手グループ企業や、上場企業も複数あり。*2025年卒実績
その他、企業の選び方に迷ったらこちらの記事を参考にしてみてください。
決めたことを正解にすることが重要
就職か、大学院進学か。これはあなたの人生における重要な決断の一つですが、決して後戻りできない、最終決定というわけではありません。多くの成功した人々が、必ずしも直線的ではない、変化に富んだキャリアパスを歩んでいます。一度選んだ道が絶対ではなく、将来的に方向転換することも、学び直しをすることも可能です。
最も大切なことは、流行や他人の意見に流されるのではなく、あなた自身の目標、価値観、状況に基づいて、十分な情報収集と自己分析を経て、現時点で最善と思える選択をすることです。どちらの道を選んだとしても、メリットとデメリットは存在します。完璧な選択、完全に不安のない選択というものは存在しないかもしれません。目指すべきは、不可能な「絶対的な確実性」ではなく、**「情報に基づいた自信」**です。つまり、選択肢を吟味し、自分の優先順位に基づいて考え抜き、現時点で可能な限り最善の選択をした、という納得感を持つことです。
この決断プロセスには、時間もエネルギーも必要です。焦らず、じっくりと自分自身と向き合い、情報を集め、信頼できる人々と対話してください。そして、一度決断したら、その選択に自信を持ち、前向きに進んでいきましょう。同時に、将来の状況変化に応じて、柔軟にキャリアを見直し、適応していく姿勢も持ち続けることが、長期的なキャリア形成においては重要になります。この選択は、あなたのキャリアという長い旅路における、一つの重要なステップなのです。あなたが自分らしい道を見つけ、自信を持って次の一歩を踏み出せることを心から応援しています。