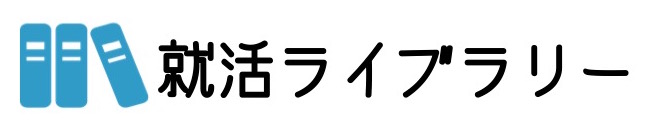こんにちは、就活ライブラリー編集長のそるてぃーです。
就職活動がうまくいかず、「就職浪人をしようか」と悩んでいる就活生の皆さん。その不安な気持ち、とてもよく分かります。周りの友人たちが次々と内定を獲得していく中で、自分だけが取り残されているような感覚に陥ることもあるでしょう。
就職浪人という選択は、決して簡単なものではありません。しかし、だからといって「終わった」と諦める必要も、焦って希望しない道に進む必要もありません。就職浪人という選択肢があることを知っておくことで、今後の人生設計により多くの可能性が見えてくるはずです。この記事では、就職浪人をした場合に新卒扱いされるのか、そして成功するためにはどのような準備が必要なのかについて、詳しく解説していきます。記事を読んで、自分がどの選択肢を選ぶことがベストなのかを判断しましょう。
就職浪人とは何か?:基本的な言葉の定義を理解しよう
就職活動を進める上で、まず理解しておくべきなのが「新卒」「既卒」「第二新卒」「就職浪人」といった用語の正確な定義です。これらの区分は、企業の採用活動や求職者の立場を大きく左右するため、正確に把握しておくことが重要です。
『新卒』の定義
新卒とは、大学・短大・専門学校・高校などを卒業見込みの学生、または卒業後間もない人を指します。従来は「卒業見込み」の学生のみを新卒と呼んでいましたが、現在では厚生労働省の指針により、卒業後3年以内の人も新卒と同等に扱うよう企業に推奨されています。
新卒の最大の特徴は、社会人経験がないことです。そのため、企業側は即戦力ではなく、将来性やポテンシャルを重視した採用を行います。また、新卒採用では一括採用が一般的で、4月入社を前提とした採用スケジュールが組まれています。
『既卒』の定義
既卒とは、大学や専門学校などを卒業したものの、正社員として就職していない人を指します。卒業後に就職活動を継続している人、フリーターとして働いている人、資格取得などの準備期間を経ている人などが該当します。
既卒の期間に明確な定義はありませんが、一般的には卒業後1年から3年程度の人を指すことが多いです。既卒者は新卒採用に応募できる場合もありますが、企業によっては中途採用枠での応募となることもあります。
『第二新卒』の定義
第二新卒とは、大学や専門学校を卒業後、一度就職したものの、短期間(一般的には1年から3年程度)で退職し、転職活動を行っている人を指します。社会人経験があるものの、その経験が浅いことが特徴です。
第二新卒の魅力は、基本的な社会人マナーやビジネススキルを身につけている一方で、前職の企業文化に染まりすぎていないため、新しい環境に適応しやすいという点です。そのため、多くの企業が第二新卒者を積極的に採用しています。
『就職浪人』の定義と位置付け
就職浪人とは、大学や専門学校を卒業したにもかかわらず、就職先が決まらずに就職活動を継続している状態の人を指します。既卒者の中でも、特に就職活動を継続している人を指すことが多く、一般的には卒業後1年以内の期間にある求職者のことを指します。
就職浪人は既卒者の一部とも言えますが、就職活動を継続しているという積極的な意味合いが強いのが特徴です。また、就職浪人期間中に資格取得や語学学習、インターンシップなどに取り組んでいる場合、企業側からも前向きな評価を得やすい傾向があります。
近年の就職活動の激化により、優秀な学生でも希望する企業に入社できないケースが増えています。特に、大手企業や人気企業への就職を目指す学生にとって、就職浪人は決して珍しい選択肢ではなくなっています。
就職浪人になる理由は様々です。第一志望の企業に入社できなかった場合、業界研究が不十分で自分に合った企業を見つけられなかった場合、面接やエントリーシートの対策が不十分だった場合など、個人によって事情は異なります。しかし、共通して言えることは、より良い就職先を見つけるための前向きな選択として捉えることができるということです。
新卒扱いの実態:企業の採用基準を詳しく解説
多くの就職浪人を検討している学生が最も気になるのは、「就職浪人をしても新卒扱いされるのか」という点でしょう。この疑問について、現在の採用市場の実態を踏まえて詳しく説明します。
結論から言えば、就職浪人をしても新卒扱いされる可能性は十分にあります。しかし、これは企業の採用方針や業界の慣習によって大きく左右されるため、一概に「必ず新卒扱いされる」とは言えません。
大手企業の多くは、卒業後3年以内を新卒扱いとする傾向があります。これは厚生労働省が推奨している「青少年雇用機会確保指針」に基づいた対応です。この指針では、大学等を卒業後3年以内の者について、新卒者と同等の扱いをするよう企業に求めています。
一方で、一部の企業では卒業後1年以内、または卒業年度の翌年度までを新卒扱いとする場合もあります。また、業界によっても基準が異なり、IT業界や外資系企業では比較的柔軟な対応を取る企業が多い一方、金融業界や公務員などでは厳格な基準を設けている場合があります。
新卒扱いされる条件として、多くの企業が重視するのは「正当な理由」です。単に就職活動がうまくいかなかったという理由だけでは、企業側に良い印象を与えることは難しいでしょう。しかし、資格取得のための勉強、語学力向上のための留学、インターンシップでの実務経験積み重ねなど、明確な目的を持って過ごした期間であれば、企業側も理解を示すことが多いです。
就職浪人のメリットとデメリット
就職浪人を選択する前に、そのメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。これらを踏まえた上で、自分にとって最適な選択を行いましょう。
就職浪人のメリット
1. 自己分析と企業研究のアップデート
まず、就職浪人の最大のメリットは、時間的余裕が生まれることです。学業と並行して行う就職活動とは異なり、就職活動に集中できる環境を作ることができます。その時間を使ってじっくりと自己分析や企業研究の時間に充てることが可能です。
新卒での就職活動でうまくいかなかった理由を挙げたときに「自己分析や企業研究が不十分だった」という人は非常に多いです。「本当に自分がやりたかった仕事は何だったのか?」「自分にはどんな強みがあり、どんな環境で活かせるのか?」「どんな企業文化が自分に合うのか?」とじっくり自分と向き合うことは内定を獲得するために非常に大事な時間の使い方です。
また、企業研究においても、これまで見てこなかった業界や企業にも目を向ける余裕が生まれます。選択肢を見直すきっかけにもなるので、自己分析と企業研究にはたっぷりと時間をかけてみましょう。
2. 資格取得などのスキルアップ
自己分析や企業研究同様、時間に余裕があるので学業中心でできなかった資格取得やインターンの参加など自分自身のスキルアップに時間を使うこともできます。得られたスキルは、面接でのアピールポイントにもなるのでとても大きなメリットとなるでしょう。
- 資格取得:志望業界や職種に関連する資格(例:TOEIC、簿記、ITパスポートなど)を取得することで、専門知識や学習意欲をアピールできる
- プログラミング学習:オンライン学習サービスやプログラミングスクールで資格取得まで目指すことが可能!IT業界志望であれば面接で武器になる!
- インターンシップ:短期・長期を問わず、企業でのインターンシップに参加し実務経験と業界・職種理解を深める
- アルバイト:漠然としたアルバイトではなく、志望業界に関連するアルバイトや、責任ある立場で働く経験を積むことで、コミュニケーション能力や問題解決能力を武器にする
3. 様々な情報収集ツールを利用できる
説明会やイベントに参加するだけでなく、OB・OG訪問を積極的に行ったり、キャリアアドバイザーに相談したりと、多角的な情報収集と準備が可能です。これにより、より自信を持って、納得のいく形で就職活動に臨むことができるでしょう。
就職浪人のデメリット
就職浪人には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。これらのリスクを理解し、対策を講じることが、後悔しないための鍵となります。
1. 経済的負担と精神的プレッシャー
一番の大きな問題は「経済的負担」と「精神的なプレッシャー」です。収入がない状態で就職活動を継続するため、生活費や就職活動費用の負担が重くなります。特に、一人暮らしをしている学生にとっては、この負担は非常に大きなものとなります。
また、精神的なプレッシャーも無視できません。同世代の友人たちが社会人として新しいスタートを切る中で、自分だけが取り残されているような感覚を抱くことがあります。このような状況が続くと、自信を失い、就職活動にも悪影響を与える可能性があります。
2. 新卒ブランドの喪失と既卒枠での採用の可能性
前述の通り、多くの企業が既卒者も新卒扱いする傾向にありますが、それでも「新卒ブランド」が持つ強みは少なからず存在します。特に大手企業や人気企業では、新卒枠の競争率が非常に高く、既卒者を受け入れる企業が限られる可能性もあります。
また、企業によっては「なぜ卒業してからすぐに就職しなかったのか」という点を厳しく問われることもあります。この質問に対して明確かつ前向きな理由を説明できなければ、不利になる可能性も十分にあります。
3. モチベーションの維持の難しさ
就職活動は長期戦であり、モチベーションの維持が非常に難しいものです。特に、明確な目標設定や計画なしに就職浪人を選択した場合、時間を持て余してしまったり、だらけてしまったりする可能性があります。「浪人したのに何も得られなかった」という後悔をしないためには、この期間をどう過ごすかという具体的な計画を立て、それを実行するための強い意志が必要になります。
4. 内定を獲得できなかった場合のリスク
もちろん、就職浪人をしたからといって必ずしも内定が獲得できるというものではありません。新卒の時よりも面接官に見られる立場は厳しくなりますし、既卒枠になった場合は競争率も高くなります。万が一、希望の就職先に内定をもらえなかった場合のことも考え、就職活動を進める覚悟を持つことは非常に大事です。

第一希望の企業に内定をもらえなくても諦めないで!関連会社や競合他社で数年間経験を積んでから、改めて本命企業にチャレンジする方法もあります。実務経験を積むことで転職市場での価値が格段に上がり、希望企業の求める人材により近づけます。
【必勝法】就職浪人を成功させる方法
就職浪人を成功させるためには、明確な戦略と準備が必要です。成功する就職浪人の特徴を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。

戦略1. 前回の就職活動の振り返り

成功する就職浪人は、前回の就職活動で何がうまくいかなかったのかを客観的に分析しています。エントリーシートの通過率、面接の通過率、最終面接での結果など、具体的な数字を把握し、どこに問題があったのかを特定することが重要です。
この分析を基に、改善すべき点を明確にし、具体的な対策を行っていきます。例えば、エントリーシートの通過率が低かった場合は、文章力の向上や企業研究の深化に取り組み、面接での通過率が低かった場合は、コミュニケーション能力の向上や面接対策に力を入れていきます。
前回の振り返りをせず闇雲に就職活動を進めても、同じところで失敗を繰り返し、大変な思いをして選択した就職浪人の期間を棒に振るってしまいます。自分で分析ができない場合は、家族や友人・キャリアセンターや就職エージェントに相談しながら進めていきましょう。
戦略2. 明確な目標設定
振り返りができたら、次は就職活動を本格的に始める前に明確な目標設定をしましょう。「なぜ就職浪人を選択したのか」「この期間で何を達成したいのか」をはっきりとさせることがポイントです。単に「良い会社に入りたい」という漠然とした目標ではなく、「○○業界の○○職種で、○○のようなスキルを活かした仕事をしたい」という具体的な目標を設定するようにしましょう。
この明確な目標設定により、就職活動の方向性が定まり、効率的な活動を行うことができます。また、面接においても、なぜその企業を選んだのか、なぜその職種を希望するのかという質問に対して、説得力のある回答をすることができます。
戦略3. 自己分析と企業研究の徹底
「前回の就職活動でやったから大丈夫」と思い込まずにもう一度、自己分析の深掘りとそれに伴った企業研究を進めていきましょう。
自己分析:本当にやりたいことは何か
「自分は何のために働くのか?」「どんな環境でならモチベーションを高く保てるのか?」といった、根源的な問いに向き合ってみることも大切です。

過去の経験の棚卸し:
学生時代の経験(学業、アルバイト、サークル、ボランティアなど)を全て書き出し、その中で「楽しかったこと」「苦労したこと」「やりがいを感じたこと」「成果を出せたこと」などを具体的に思い出しましょう。その際、なぜそう感じたのか、どのような行動をとったのかを深掘りしてみましょう。自分の価値観を見つけることができるはずです。
価値観の明確化:
仕事において何を最も重視するのか?(例:給与、安定性、成長性、やりがい、人間関係、社会貢献、ワークライフバランスなど)優先順位をつけてみましょう。全てを叶える企業はなかなかないので、どうしても外せない条件とあったら嬉しい程度のものとの差別化も大切です。
得意なこと・苦手なことの把握:
どのような作業や役割が得意で、どのようなことが苦手なのかを認識します。これは、職種選びの大きなヒントになります。
将来のキャリアプラン:
5年後、10年後、どんな自分になっていたいのか、どんな働き方をしていたいのか、具体的に想像してみましょう。企業は長期的に働いてくれる人を求めているので長期的なキャリアプランを持っている方が好印象になります。
自己分析ツール(MBTI診断、ストレングスファインダーなど)を活用するのも良いですが、それに頼りすぎるのではなく、あくまで自分自身で考える材料として活用しましょう。
企業研究
すべての業界や企業を網羅的に調べるのではなく、自身の軸に合致する業界や企業に絞って深く掘り下げていきましょう。
企業研究のツールとしては①書籍、②企業サイト、③OB・OG訪問、④口コミサイトが挙げられます。それぞれの特徴を理解してバランスよく情報を収集するようにしていきましょう。

- 書籍:書籍では、業界全体の動向や企業の成長性を理解することができます。
- 企業サイト:会社概要や事業内容、最新のニュースリリースなどが掲載されており、その企業がどのような方向性で成長しようとしているのかを知ることができます。
- OB・OG訪問:求人情報や企業サイトだけではわからない「働く環境のリアル」を知ることができます。
- 口コミサイト:現役社員や元社員が投稿した口コミをみることができるので、企業の実態を客観的に判断することができます。
戦略4. 就職浪人中の「空白期間」を作らない
就職浪人という期間は、企業から見れば「空白期間」と捉えられる可能性があります。この期間をどのように過ごしたかが、面接での重要なポイントになります。ただ漫然と過ごすのではなく、自己分析や企業研究を通して見えてきた、志望する業界や職種で求められるスキルを習得することや興味のある企業のインターンに参加することをおすすめします。
スキル取得については、グローバル企業や外資系企業を志望するなら、TOEICのスコアアップや英会話力の向上は必須です。オンライン英会話や語学学校に通うのも良いでしょう。
プログラミング(Python、Javaなど)、Webデザイン、データ分析など、ITスキルは多くの業界で需要が高まっています。オンライン学習サービスやプログラミングスクールを活用することで実践的なスキルまで習得することができます。講座だけではなく就職サポートも行ってくれるスクールもあるので、IT業界を目指す人は特にスクール情報をチェックしてみましょう!
ビジネススキルの習得も面接や入社後にも役立つのでおすすめです。論理的思考力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力など、社会人に必須のスキルを磨くために、ビジネス系のイベントやセミナーに出席する方法があります。
あれもこれも手をつけるのではなく、自分にとって一番良いスキル習得を選択しましょう!
戦略5. 念入りの準備と実践
前回の就職活動の振り返りで気づいた自分の弱点を中心に、選考対策を行っていきましょう。
- 応募書類の見直しとブラッシュアップ:
自己分析と企業研究の成果を基に、より具体的で説得力のある自己PRと志望動機を作成しましょう。過去の経験と将来の目標を関連付け、なぜその企業でなければならないのか、なぜ自分はその企業に貢献できるのかを明確に伝えるようにしましょう。 - 面接対策:
過去の就活で聞かれたことを思い出し想定質問集を作成しましょう。その際、第三者に必ずフィードバックをもらうことが大切です。また、話す内容だけでなく表情、声のトーン、話し方、姿勢なども意識しましょう。清潔感のある身だしなみも大切です。 - 情報収集:
在学中とは異なり、リアルタイムな就活情報を得られる環境は少なくなります。そのため、自分から情報を取りに行かなけらばなりません。大学のキャリアセンターやOB・OG訪問、就職エージェントを活用して常に就活のトレンドを入手していきましょう。
※重要※:面接での効果的なアピール方法
就職浪人に関する質問は必ず聞かれます。
就職浪人生が面接で成功するためには、この期間をいかに有効活用したかを効果的にアピールする必要があります。「なぜ就職浪人をしたのか」「その期間に何を学び、どのように成長したのか」を相手が納得できるように伝えなければ、就職活動はうまくいきません。
単なる事実の羅列ではなく、ストーリー性のある構成で話すことが重要です。なぜそのような選択をしたのか、どのような困難に直面したのか、それをどのように乗り越えたのか、その結果何を学んだのかという流れで説明しましょう。
また、就職浪人期間中に達成した具体的な成果を明確に提示することで、説得力のあるアピールができます。資格取得、語学力向上、プロジェクトの完成など、数値化できる成果があれば積極的に伝えましょう。さらに、これらの成果を通じて身につけたスキルや知識が、希望する職種でどのように活かせるのかも併せて説明することで、企業側により強い印象を与えることができます。企業側は、長期的に活躍できる人材を求めています。就職浪人期間中の経験が、将来のキャリア形成にどのように活かされるのかも説明できれば企業側により好印象を与えることができます。
就職浪人期間中の過ごし方
就職浪人を決めたら、漫然と日々を過ごすのではなく、具体的なプランを立て、計画的に行動することが重要です。しっかりとタイムスケジュールを組むことでだらけることなく、メリハリを持って生活しましょう。
- 9:00-10:00最新のニュースチェック、業界ニュースの確認
- 10:00-12:00自己分析、企業研究、ES作成、資格勉強など、集中力の必要な作業
- 12:00-13:00昼食
- 13:00-15:00スキルアップのための学習(プログラミング、語学など)
- 15:00-17:00就職エージェントとの面談、OB・OG訪問、インターンシップへの参加、アルバイトなど
- 17:00-18:00運動や気分転換(散歩、筋トレなど)
- 18:00-19:00タイトル
- 19:00-21:00面接練習、情報収集、その日の振り返り、翌日の準備(履歴書の最終チェックなど)
- 21:00-23:00自由時間
- 23:00就寝
point1. 集中力の必要な作業は午前中に
朝一で、ニュースを見てトレンドをチェックし時事問題にも対応できるように情報収集は欠かさないようにすることが大切です。また、自己分析や企業研究・エントリーシートの作成など集中力が必要な作業は、午前中にまとめて行いましょう。

家で集中できない場合は、大学の図書館やコワーキングスペースをうまく活用して集中できる環境を自分で作っていきましょう!
point2. 適度な運動や気分転換を忘れずに
適度な運動は、ストレス解消や気分転換に繋がります。また、気分転換になる趣味の時間も大切にしましょう。就職活動漬けになりすぎると、精神的に疲弊してしまいます。
また、就職浪人期間は経済的負担も大きくなるので気分転換を兼ねてアルバイトや報酬型のインターンに参加することもおすすめです。
point3. 【超重要】周囲のサポートを活用する
就職浪人期間は、想像しているよりも孤独を感じやすい期間です。一人で抱え込まず、周囲のサポートを積極的に活用しましょう。特に大学のキャリアセンターや就職エージェントは相談に乗ってくれるだけでなく、就職活動のサポートまで行ってくれます。最新の就職活動の情報などは、学内にいないと得られない場合が多いので、就職浪人している人は就職エージェントから情報を得ることは内定までの近道となるでしょう。

就職エージェントを利用することで客観的なアドバイスをもらうことができるので、就職活動の質を上げることができます。また、自分に合った求人や特別推薦枠を用意してくれる場合があるので、うまく活用することが内定獲得の鍵になります。
採用責任者そるてぃーおすすめの就職エージェントをまとめた記事があるので是非チェックしてみてください。
就職浪人は「失敗」ではなく「未来への投資」
就職浪人は決してネガティブな選択ではありません。この期間を有効活用し、明確な目標を持って取り組むことで、より良いキャリアのスタートを切ることができます。
重要なのは、就職浪人期間中に何を達成したいのかを明確にし、その目標に向かって継続的に努力することです。また、企業側の採用基準や求める人物像を正確に理解し、それに合わせた対策を講じることも必要です。就職浪人という選択に不安を感じるのは自然なことですが、この期間を自分自身の成長と将来のキャリア形成のための重要な投資期間と捉えることで、より前向きに取り組むことができるでしょう。
最後に、就職浪人を成功させるためには、一人で悩まず、家族や友人・就職エージェントなどのサポートを積極的に活用することも重要です。多くの人の支えを得ながら、自分なりのキャリアを築いてきましょう。